私自身、うつ病の経験があり。その当時は仕事をしながら心療内科へ受診をしていました。医師からは、「いつでも会社を休めるように診断書を書いてあげようか」と助言がありましたが、一旦断り上司に相談をしました。
幸いのことに、職場を変えていただき、休職をせずに仕事を続けることができました。上司との信頼関係があったからこそ出来たことだと思います。
私自身のケースは、まだうつ病の症状が重くないので、比較的スムーズに事が進みましたが、それこそ「精神障害者保健福祉手帳3級」を持っておられる方など、どうしたら工場で働くことができるでしょうか?
私が知る限りでは、福祉サービスを利用する手段があります。私も、専門家ではないので、詳しいことはわかりませんが身近にいた方を参考に解説をしていきます。
ステップ1 まずは、心療内科へ相談する

うつ病で「障害者手帳」を取得していない場合は、医師の診断が必要となっていきます。基準項目としては「躁うつ病」と該当します。なお、うつ病は精神障害者手帳の取得対象となります。
※ただし、「精神障害者保健福祉手帳3級」を取得するためには、 初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。
ステップ2 役所・役場の福祉課へ相談する
心の病は、体の病と違い目に見えないものです。外見上判断できないことから、いくらうつ病が酷いと訴えたとしても、行政側は認めてくれません。そのためには医師の診断書や障害者手帳が証となっていきます。
まずは、福祉課の窓口へ受付をします。担当の相談員が来られるので、今自分が置かれている状況や悩みを打ち明けます。
私が見た経験では相談員のほうから、自立支援という形でサポート受けることになると思います。そうなっていくと、長期の支援となるので、社会福協議会などの相談員が担当します。
ステップ3 相談員から自立支援のサポートを受ける

私の知人は、自立支援サポートを受ける前に、就職をしてしまい、幸いそこの職場が自分に適しており、主治医からは、フルタイムは禁止されていましたが、うつ病でありながらもやりがいを感じ、今もその仕事は続いています。
私の経験上の解説は、ここまでとなり僅かなことしか語れず申し訳ございませんが、ここから先は、厚生労働省の資料をもとに解説をしていきます。
生活困窮者自立支援制度
平成25年12月、生活困窮者自立支援法が成立され、”生活保護受給者以外の生活困窮者への支援を強化するものである”とのこと。
セーフティーネットを活用して生活を安定させる
セーフティーネットとは、生活や経済活動などにおいて、さまざまなリスクを回避するための制度です。今回の場合は「第1ネット」「第2ネット」「第3ネット」の仕組みがあり。簡単に解説をします。
■第1ネット 安定した雇用を土台に「社会保険制度」や「労働保険制度」。
■第2ネット 「求職者支援制度」と「生活困窮者対策」。
■第3ネット 「生活保護」。
○生活困窮者自立制度は、第2ネットに該当し、自立支援に向けて行う。なお、当然ながら生活保護が必要な人には適切につなぐなど、第3ネットを利用し両輪として対策をする。
参考資料(厚生労働省):自立相談支援事業の手引き(PDF)
ステップ4 就労継続支援A型を利用してみる
就労継続支援とは、障害や難病など一般就労が困難の人を対象とした働く環境が提供されます。もちろん働いた分、収入は確保できます。
就労継続支援には、A型とB型があり、それぞれどういったものか解説をしていきます。
就労継続支援A型とは
障害や難病がある方が雇用契約を結んで一定の支援を受けながら働くことができる福祉サービスです。障害者総合支援法に基づくサービスで、「雇用型」とも呼ばれます。
主な支援内容
| 支援項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用契約 | 正式な雇用契約を結び、就労機会の提供や訓練を受けられます |
| 能力向上支援 | 就労に必要な知識や能力の向上を図るための訓練を実施 |
| キャリア支援 | 一般企業等への移行を目指す場合の技能習得支援 |
利用対象者(原則18歳~65歳未満)
- 特別支援学校卒業後、一般企業での就職に結びつかなかった方
- 就労移行支援事業所利用後、一般企業での就職に結びつかなかった方
- 一般企業での就労経験があり、現在離職中の方
- 障害者手帳は必須ではありません。医師の診断があれば、手帳をお持ちでない方も利用できる可能性があります。
利用までの流れ
自治体での受給者証の発行が必要です。申請から支給決定まで約2ヶ月かかることが多いため、事業所探しと並行して進めることをお勧めします。
就労継続支援A型の仕事内容は幅広い
就労継続支援A型の仕事内容とは、一般の会社と同じように様々な仕事がありますが、精神的負荷や肉体的負荷が少ない仕事がメインとなります。
就労継続支援A型の事業所では、たとえばこんな仕事があります。
- データ入力: パソコンを使って、文字を打ち込んだり、書類を作ったりする仕事。
- 清掃: 事務所の中や外をきれいに掃除するお仕事。
- 農作業: 野菜や果物を育てたり、収穫したりするお仕事(農作業をしている事業所の場合)。
- 販売: 自分たちで作ったものや、仕入れたものを売るお仕事(販売をしている事業所の場合)。
- 車部品の加工:工場の仕事が希望の方にはうってつけ。
これらの仕事は、働く人の得意なことや希望に合わせて割り振られるから、無理なく働くことができます。さらに、事業所によっては、これ以外の仕事をしているところもあります。
就労継続支援A型では、仕事をすることで、働くためのスキルを身につけたり、もっとステップアップして、普通の会社で働くためのサポートもしているところが魅力のひとつです。
給与について(令和4年度実績)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 平均月収 | 83,551円 |
| 平均時給 | 947円 |
※地域の最低賃金以上が保障されますが、一般雇用と比べて就労時間が短い場合が多いため、月収が低くなる傾向があります。
就労継続支援B型とは
障害や難病などの理由で一般企業での就職が困難な方に対して、就労の機会や生産活動の場を提供する障害福祉サービスです。
主な支援内容
| 支援項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用契約 | 事業所に通って作業をすることになりますが、雇用契約は結びません。 |
| 能力向上支援 | 就労に必要な知識や能力の向上を目的としています。 |
| キャリア支援 | 一般企業での就職に必要な知識をつけるなどの就職支援 |
利用対象者(年齢は定めなし)
- 就労経験があり、年齢や体力の面で、一般企業に雇用されることが困難になった方。
- 50歳以上の方、または障害基礎年金1級を受給している方。
- 一定の条件を満たした場合、65歳以上の方も利用可能になる場合もあります。
- 就労移行支援事業者などの公正な評価により、仕事をする上での困りごとが分かっていて、かつ仕事に慣れていくために、B型事業所が適切だと判断された方。
- 障害者手帳は必須ではありません。医師の診断があれば、手帳をお持ちでない方も利用できる可能性があります。
利用までの流れ
B型の事業所を利用するには、まず主治医に相談し、その後、市町村の窓口で申請手続きを行います。その後、相談支援事業所で利用計画を作成してもらい、受給者証を受け取ってから、希望するB型事業所と契約を結ぶことで、利用を開始することができます。
就労継続支援B型の仕事内容も幅広い
就労継続支援B型の仕事内容とは、精神的負荷や肉体的負荷が少ない仕事となり、以下のような軽作業を中心とした仕事を行います。
- 農作業
- 部品の加工
- 手工芸(製品への刺繍など)
- お菓子作り(パン・クッキーなど)
- 飲食店での調理
- クリーニング作業
- WEBサイト制作
仕事内容は、事業所によっておこなう作業が異なります。利用者の方の状況や、事業所の規模や方針によって、現場の作業や事務的な作業など、担当する仕事はさまざまです。そのため、ご自身の経験や興味に合った仕事を選ぶことが大切です。
給与について(令和4年度実績)
就労継続支援B型では雇用契約を結ばないので、給料ではなく代わりに働いた分だけの工賃が貰えます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 平均工賃(月額 | 17,031円 |
| 平均時給 | 243円 |
就労継続支援A型とB型どちらを選べばいいか

就労継続支援B型は長時間の就労が困難な方や体調や精神面で不安定な方が自分のペースで働くのに向いており、A型はある程度安定して仕事をすることができる方に向いています。
収入面や一般雇用へ働きたいと願えば、A型のほうが近道でしょう。B型と比較すれば精神的・肉体的負荷はかかりますが、収入面から考えますとA型のほうをおすすめします。
まとめ
うつ病で仕事探しに悩んでいる方へ。この記事では、うつ病で働くことへの不安を解消し、自分に合った仕事を見つけるためのヒントを紹介します。まずは、心療内科を受診し、医師に相談することが大切です。その後、役所や福祉課に相談することで、自立支援制度を利用することができます。就労継続支援A型やB型といった、障害のある人が働くための支援サービスを活用し。これらのサービスを利用することで、自分のペースで仕事に取り組むことができ、社会復帰への一歩を踏み出すことができます。まずは、一歩踏み出して、自分に合った支援サービスを探してみましょう。
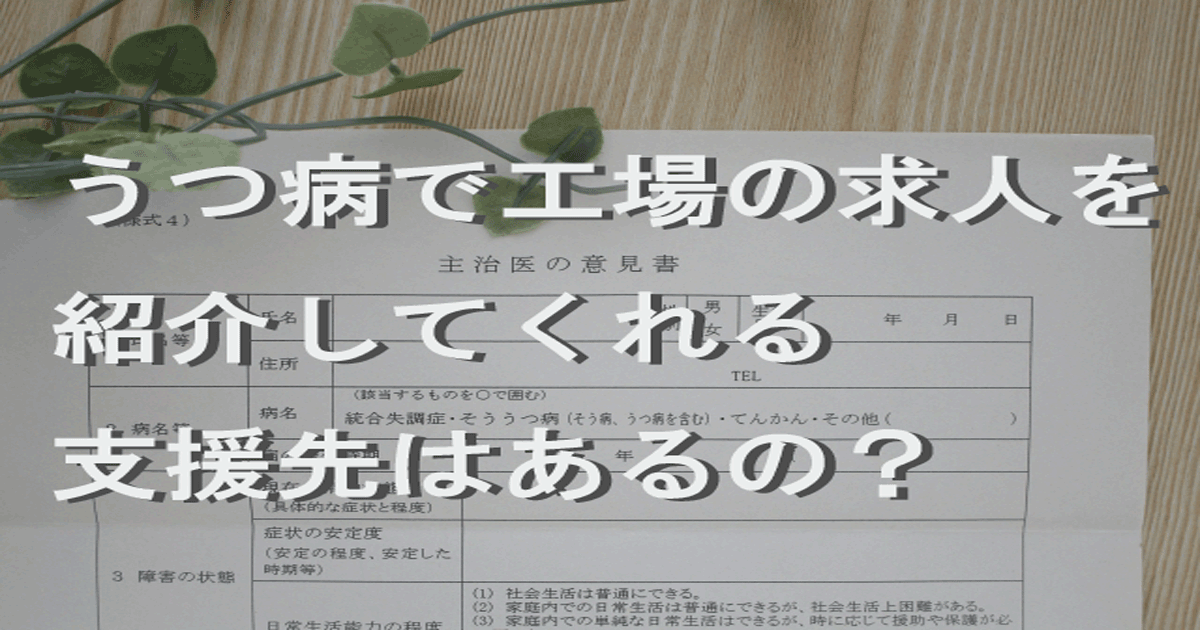
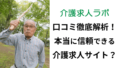
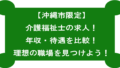
コメント